皮ふ科・アレルギー科
皮ふ科・アレルギー科
皮膚は私たちが目で直接見ることのできる臓器です。
そして身体の一番外表面にあるということから、外的な刺激にさらされやすく、かつ内部からの影響も受けやすい臓器でもあります。
皮膚疾患は目に見える分、悩みも多いかと思います。
皮膚専門医として、赤ちゃんから御高齢の方の皮膚に関するトラブルに向き合っております。
お気軽に相談ください。

受診される方の例
皮ふ科画像送信用メールアドレスは、下記になります。
online.homecareclinic@gmail.com
※画像をお送りいただく場合にお願いしたいこと
①件名にはフルネーム(氏名)を記載してください
②患部の全体像とアップの写真を、できるだけピントを合わせて撮影してください
アトピー性皮膚炎
かゆみを伴う湿疹が慢性的に繰り返される病気です。家族にアレルギー体質(喘息、花粉症など)のある方や「IgE抗体」が多い体質の方に発症しやすい傾向があります。遺伝的な体質に加え、環境要因も関与します。乳幼児期の湿疹は食物アレルギーのリスクを高めるため、早期治療が重要です。
治療の目標
症状がない、または軽く日常生活に支障がない状態を目指します。
アトピー性皮膚炎は治療で症状を抑え、薬の使用を減らすことが可能です。
治療方法
1薬物療法
| ステロイド外用薬 | 基本的治療薬。適切に使用することで副作用を抑えます。 |
|---|---|
| 非ステロイド外用薬 | 乳幼児でも使いやすい薬や刺激の少ない薬が増えています。 例: タクロリムス、デルゴシチニブ軟膏など。 |
| プロアクティブ療法 | 症状が落ち着いた後も外用薬を徐々に減らし、保湿剤だけでコントロールする方法です。 |
| 重症例への対応 | 内服薬(JAK阻害薬など)や注射薬(生物学的製剤)を使用します。 |
2スキンケア
- 毎日、皮膚を清潔にし、保湿をします。乾燥や湿疹が出た場合は早めに皮膚科を受診しましょう。
3悪化因子対策
- 食物、ダニ、花粉、汗、ストレスなどが悪化因子になる場合があります。これらを取り除くことが治療を助けます。
患者様へ
近年、アトピー性皮膚炎の治療は飛躍的に進歩し、「治らない病気」から「克服できる病気」へと変化しています。 ただし、治療には患者様ご自身やご家族の協力が不可欠です。当院では、初診時に、治療の目標を共有し、外用指導を行っております。 私たちは患者様やご家族のご負担を少しでも軽減できるよう、サポートし、アトピー性皮膚炎に悩まされずに、日常生活が生き生きと送れるお手伝いがしたいと思っております。
手湿疹
手に発生する湿疹で、乾燥、かゆみ、赤み、ひび割れが主な症状です。刺激物やアレルギー、乾燥が原因となり、慢性化しやすいのが特徴です。
治療法
| ステロイド外用薬 | 炎症を抑える基本治療。1日3回適切に塗布します。 |
|---|---|
| 保湿剤 | 無香料・低刺激の保湿剤で皮膚のバリア機能を回復。 |
| 抗ヒスタミン薬 | かゆみが強い場合に内服で使用。 |
| 漢方薬 | 症状や体質に応じて処方される場合があります。 |
日常での注意点
| 手洗い後の保湿 | 保湿剤で皮膚のバリアを保護しましょう。 |
|---|---|
| 手袋の使用 | 家事や水仕事ではゴム手袋を使用し、内側に綿手袋を重ねるのも1つの方法です。 |
| ぬるま湯の使用 | 熱いお湯は避けて、乾燥を防ぎましょう。 |
じんましん(蕁麻疹)
皮膚に蚊に刺されたような赤みやふくらみが現れ、強いかゆみを伴う皮膚疾患です。
多くの場合、数時間から1日以内に消えますが、新しい場所に繰り返し出ることもあります。
治療
| 抗ヒスタミン薬 (内服薬) |
|
|---|---|
| 追加治療 | 抗ヒスタミン薬のみで効果が乏しい場合、抗ロイコトリエン薬、トラネキサム酸、注射薬などを使用することがあります。 |
ニキビ(尋常性ざ瘡)
原因
毛穴が詰まり、そこに皮脂の過剰分泌により皮脂が溜まり、アクネ菌が繁殖することによって起きます。
ホルモンバランス、食生活、ストレス、紫外線なども悪化要因になります。
症状
- 白・黒ニキビ(炎症のない初期状態)
- 赤ニキビ(炎症を伴う赤み)
- 膿ニキビ(膿を伴う状態)
- 膿疱性ニキビ(深い炎症で跡が残りやすい)
などの色々な見え方をします。
治療法
1 保険診療
- 毛穴の詰まりを取る: 過酸化ベンゾイル、アダパレンなどの外用薬を使用。
- アクネ菌を抑える: 抗生剤や抗菌作用のある外用薬を併用。
- 状況により抗生剤の内服や漢方薬を組み合わせます。
2 自費診療
- ビタミンCローション: 炎症や皮脂を抑制。ニキビ跡にも有効と言われています。
- アゼライン酸: 毛穴ケアや色素沈着抑制。
- レーザー治療: 深い炎症に対応、5~6回の施術で効果。
- ガウディスキン療法: 集中的な肌質改善プログラム。
日常生活の注意点
- 正しい洗顔を1日2回優しく行う。
- 血糖値が急激に上がる甘いものを控え、バランスの取れた食事を。
- 十分な睡眠とストレスの軽減を心がける。
- 紫外線対策を行い、刺激の少ない化粧品(ノンコメドジェニック)を使用する。
初診の方には外用指導を行い、ニキビの治療薬で初期に出やすい刺激感の回避に努めております。
ニキビ治療に関して、ご不安な点などありましたら、遠慮なくご相談ください。
単純ヘルペス
(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)
口唇ヘルペスとは?
単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が原因で、唇や口周辺に水ぶくれや痛みを伴う症状が現れます。
ウイルスは神経節に潜伏し、免疫力が低下すると再発します。
性器ヘルペスとは?
HSV-1または2型(HSV-2)が原因で、性器や周辺に水ぶくれや潰瘍を引き起こします。
初感染では重い症状が出ることがありますが、再発時は軽度の場合が多いです。
治療法
| 抗ウイルス薬 | バルトレックス®、ファムビル®を5日間内服 |
|---|---|
| PIT療法 (Patient Initiated Therapy患者さんが自分で開始できる方法) |
初期段階でアメナリーフ®、ファムビル®を単回あるいは2回の服用頂き、症状の悪化を防ぐ方法です。 |
| 再発抑制療法 (性器ヘルペスのみ) |
再発が頻繁な場合、低用量の抗ウイルス薬を長期間服用し、再発頻度を減少する治療です。 |
帯状疱疹
水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で発症する疾患です。水ぼうそう(水痘)として初感染後、ウイルスは神経節に潜伏し、免疫力の低下やストレスをきっかけに再活性化して発症します。
症状
- 痛みを伴う赤い発疹や水疱が片側の神経に沿って現れる。
- 水疱が治癒後も痛みが続く「帯状疱疹後神経痛」が残る場合があります。
治療法
| 抗ウイルス薬 | アシクロビルやバラシクロビルなどを使用。発症後72時間以内の服用で効果的。 |
|---|---|
| 鎮痛薬 | NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や、神経痛用薬(プレガバリン、ガバペンチン)。 |
予防とケア
| ワクチン接種 | 帯状疱疹や帯状疱疹後神経痛の予防に効果的です。 |
|---|---|
| 免疫力向上 | 十分な休息とバランスの取れた食事を心がけましょう。 |
帯状疱疹ワクチン
| 発症予防 | 帯状疱疹の発症リスクを大幅に軽減。 |
|---|---|
| 後遺症予防 | 帯状疱疹後神経痛(PHN)の発症を防ぎます。 |
ワクチンの種類
| 生ワクチン(ゾスタバックス®) 7500円 |
|
|---|---|
| 接種回数 | 1回 |
| 効果 | 発症リスクを50~60%軽減、神経痛の予防効果67%程度。 |
| 維持期間 | 約5~7年 |
| 対象 | 50歳以上(免疫抑制状態の方は不可) |
| 不活化ワクチン(シングリックス®) 22000円×2 |
|
|---|---|
| 接種回数 | 2回(2~6か月間隔) |
| 効果 | 発症リスクを90%以上軽減。神経痛の予防効果88%程度。 |
| 維持期間 | 10年以上 |
| 対象 | 50歳以上、または18歳以上で帯状疱疹のリスクの高い方。 |
鶏眼(うおのめ)
と胼胝(たこ)
鶏眼(うおのめ)とは?
特定部分の皮膚が硬くなり、中心の芯が神経を圧迫して痛みを伴います。
足に合わない靴や足の変形が主な原因です。
胼胝(たこ)とは?
皮膚が慢性的な刺激を受けて厚くなる状態です。
芯はなく、広い範囲で硬く盛り上がります。通常は痛みがありません。
治療法
| うおのめ | |
|---|---|
| 芯の除去 | 痛みの原因となる芯を切除。 |
| スピール膏 | 角質を柔らかくし処置を行います。 |
| たこ | |
|---|---|
| 角質除去 | 軟膏やスピール膏で柔らかくしたり、必要に応じて除去。 |
| 生活習慣改善 | 足への負担を軽減。 |
陥入爪・巻き爪
陥入爪とは?
爪の端が皮膚に食い込んで痛みや腫れを引き起こす状態です。
巻き爪や深爪、靴の圧迫が原因になることがあります。
巻き爪とは?
爪が丸く巻いた状態です。
痛みはありませんが、進行すると陥入爪になることがあります。
原因は遺伝、歩き方、靴の圧迫などです。
治療法
| 陥入爪 | |
|---|---|
| 抗生剤 (内服・外用) |
赤みや膿のある場合に使用。 |
| 肉芽処理 | 液体窒素で膨らんだ皮膚を除去。 |
| テーピング | 爪が皮膚に当たらないよう固定。 |
| 爪切り | 局所麻酔下で爪を斜めにカット。 |
| 巻き爪 (保険適応外) |
|
|---|---|
| クリップ法 | 合金プレートで爪の形を矯正(5225円〜)。 |
| 巻き爪 マイスター |
ワイヤーで爪を矯正(5840円~) |
※保険適応外治療では別途初診料1800円、再診料800円がかかります。
※手術が必要と医師が判断した患者さんは、手術目的にて他院へ紹介することもございます。
予防法
- 爪は「スクエアオフカット」(四角い形)で整え、深爪を避けましょう。
- 窮屈な靴や靴下を避けましょう。
- 足を清潔に保ちましょう。
水虫
足白癬(水虫)
主な症状
| 趾間型 | 指の間(特に小指周辺)の白いふやけた皮膚やひび割れ、かゆみ。 |
|---|---|
| 小水疱型 | 足の土踏まずや側面の水ぶくれとかゆみ。 |
| 角質増殖型 | 足裏全体の皮膚が硬くなり、ひび割れやかさつき。 |
治療法
| 外用薬 | 抗真菌薬を患部より広めに塗布し、最低3か月継続します。 |
|---|---|
| 内服薬 | 外用薬で改善しない場合や角化が厚い例では、抗真菌薬の飲み薬を使用。治療期間は3か月以上。 |
爪白癬(爪の水虫)
爪白癬とは爪に白癬菌が感染し、白や黄色に変色したり、硬く厚くなったり、かけやすくなる病気です。
治療法
| 外用薬 | 表在型の爪白癬に効果があり、爪専用の抗真菌薬を塗布。治療期間は最低1年必要。 |
|---|---|
| 内服薬 | 奥深くまで感染した場合に有効。治療期間は3か月~1年で、血液検査を定期的に行います。 |
予防とケア
- 足を清潔に保ち、特に指の間をよく乾燥させる。
- 公共施設では裸足を避け、スリッパを利用。
- 家族間でタオルやスリッパの共有を控える。
わき汗
多汗
原発性腋窩多汗症は、脇に必要以上の汗をかく状態です。
暑さだけでなく、緊張や日常生活の中でも大量に汗をかき、生活に支障をきたす疾患です。
エクリン腺という汗を出すところから大量の汗が出ることにより生じます。
治療法
| 外用薬 (保険適応) |
|
|---|---|
| アルミニウム製剤 (保険適応外) |
クロルヒドロキシアルミニウム配合のジェル(キュアデイズ)2750円(税込)。 |
| 内服薬 (保険適応) |
全身の汗を抑えますが、副作用(口の渇きや便秘)が出る可能性があります。 |
| ボツリヌス毒素注射 (保険適応) |
汗腺の神経を抑制し、効果は4~6か月持続します。 𦚰ボトックスの 資料はこちら |
ニオイ
主にアポクリン腺という脇にある汗を出すところから出る、汗のニオイによるものです。
症状と特徴
| ツンとした臭いや酸っぱい臭い | アポクリン腺が関与したニオイです。 |
|---|---|
| 衣類の黄ばみ | 汗による影響。 |
| 汗と雑菌の繁殖 | 汗があることによって雑菌が増殖し、ニオイが生じることもあります。 |
当院の治療法(保険適応外)
| 汗を抑える製剤 | クロルヒドロキシアルミニウム配合ジェル(キュアデイズ)2750円(税込)。 |
|---|---|
| 雑菌の繁殖を抑えるケア | 雑菌を抑えるボディソープ(Dウォッシュ)2530円(税込)。 |
脱毛症
髪が部分的または広範囲に抜ける状態で、原因や種類によって治療法が異なります。
主な種類と特徴
| 円形脱毛症 | 突然円形の脱毛斑ができる自己免疫疾患。 |
|---|---|
| 男性型脱毛症(AGA) | 前頭部や頭頂部の薄毛(進行性)。 |
| 女性の男性型脱毛症 | 頭頂部を中心に髪が薄くなる。 |
| 休止期脱毛症 | ストレスや病気で毛周期が乱れ、大量に抜ける。 |
| 牽引性脱毛症 | 髪を引っ張るヘアスタイルが原因。 |
検査方法
視診、問診、拡大鏡(ダーモスコピー)や血液検査などを行う場合があります。
治療法
| 円形脱毛症 |
|
|---|---|
| 男性型脱毛症(AGA)(保険適応外) | ミノキシジル外用薬、フィナステリド、デュタステリドの内服薬。 |
| 女性の男性型脱毛症(保険適応外) | ミノキシジル(女性用)。 |
| 休止期脱毛症 | ストレス軽減や生活習慣改善で自然回復を目指す。 |
| 牽引性脱毛症 | 髪を引っ張るスタイルを避け、頭皮を休ませる。 |
掌蹠膿疱症
(しょうせきのうほうしょう)
手のひらや足の裏に膿を伴う水ぶくれ(膿疱)ができる疾患で、感染症ではありません。
慢性化することが多く、日常生活に影響を及ぼします。
原因と悪化因子
| 免疫異常 | 過剰な免疫反応による炎症が主な原因。 |
|---|---|
| 悪化因子 |
|
治療法
| 外用療法 |
|
|---|---|
| 光線療法 | ナローバンドUVB: 紫外線で免疫反応を調整。 |
| 悪化因子への対応 | 禁煙や歯科治療、金属アレルギーの対応が必要な場合もあります。 |
尋常性乾癬
(じんじょうせいかんせん)
尋常性乾癬とは、表面が銀白色の鱗屑で覆われた境界のはっきりした赤い発疹(紅斑)が皮膚に生じる疾患です。
好発部位は頭皮、肘、膝、腰などです。
治療法
| 外用療法 |
|
|---|---|
| 光線療法 | ナローバンドUVB療法で皮膚の免疫反応を調整。 |
| 内服療法 |
|
| 生物学的製剤 |
難治性乾癬に有効で、生活の質を大きく改善させます。 ※当院では導入開始はできませんが、ほかの施設で開始して安定してきた場合の継続加療は可能なことがありますので、その際はお問い合わせください。 |
尋常性白斑
(じんじょうせいはくはん)
尋常性白斑とは?
皮膚の一部が白くなる疾患で、メラニン色素を作る細胞(メラノサイト)が減少・消失することで発症します。
全人口の1~2%に見られ、年齢や性別を問わず発症します。顔、手足、肘、膝などに左右対称に発症することが多いです。
治療法
| 外用薬 | ステロイド外用薬など |
|---|---|
| 光線療法 | ナローバンドUVB療法でメラノサイトを活性化。週1~3回の通院が必要。 |
熱傷
熱傷は、お湯や油、電気などの温度が高いものに触れて皮膚が傷つく状態です。
深さにより赤みや痛み、水疱が生じたりします。
やけどしたらやること
- 火傷したらすぐ、患部を冷水15〜30分冷やす
- 水ぶくれがあれば、清潔なガーゼで保護する。
- 広範囲の熱傷、顔や関節などのデリケートな部位の損傷、大きな水ぶくれがある場合は医療機関へ。
治療法
熱傷の深さ、広さに応じて、白色ワセリンを用いたり、深い傷の場合は、フィブラストスプレー、プロスタンディン軟膏、ゲーべンクリームなどを用いる場合もあります。
予防法
- 熱い調理器具や熱いお茶などは子どもの手が届かない場所に。
- 寝る前に湯たんぽを外す、アイロンやストーブを使用後すぐ片付ける。
小児アトピー性皮膚炎
アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹が繰り返し出る慢性的な皮膚の病気です。特に小児期に発症することが多く、乳児期(0歳〜1歳)から症状がみられることもあります。
原因と特徴
皮膚のバリア機能が弱いことと、アレルギー反応が関係しています。ダニ・ハウスダスト・花粉・食べ物などのアレルギー物質や、汗・衣類の摩擦などの物理的な刺激で炎症を起こしやすい状態になります。
湿疹が出やすい部位は、乳児では頬や額、頭、首回りに多く幼児・学童期ではひじやひざの裏、首、手首足首など関節の内側です。
治療法
アトピー性皮膚炎は①スキンケア、②薬による炎症コントロール、③かゆみの対策が重要です。
1 スキンケア(皮膚のバリア機能を守る)
- 保湿ケア: 毎日たっぷりと保湿剤を塗ることで肌のバリアを整えましょう。
- 洗浄は刺激の少ない石けんを。
- 汗をかいたらすぐに拭き取り、シャワーで流すなど、刺激から回避しましょう。
2 薬による炎症のコントロール
- 基本的薬物治療は、ステロイド外用薬です。
- ステロイドは「怖い」と思われがちですが、正しく使えれば安全で、かゆみや炎症を早く抑えることができます。
- ただし、最近ではアトピー性皮膚炎用の新しい抗炎症外用薬も増えてきているので、それらを併用しながら、ステロイドを減らしていくことも可能になってきています。
3 かゆみの対策(悪化因子対策)
- かゆみが強いときは、抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬)を内服することがあります。
- 爪を短く切る
- 部屋の湿度管理(50〜60%)を行い、ダニやハウスダストを減らすことで悪化因子を減らす
患者様とそのご家族へ
当院は小児科と併設の皮膚科であり、比較的小児の皮膚疾患のお子様も多くいらっしゃいます。「夜にかゆがって眠れない」「薬を塗ってもすぐにぶり返す」「何をしても乾燥してしまう」など、お悩みに寄り添い、一緒に治療をしていきたいと思っておりますので、お気軽にご相談ください。
乳児湿疹
乳児湿疹は、生後間もない赤ちゃんの皮膚に現れるさまざまな湿疹の総称です。
皮膚が薄くデリケートな乳児期には、皮脂や汗の分泌、外的刺激によって皮膚のトラブルが起きやすく、いくつかのタイプに分類されます。
乳児湿疹の主な種類と特徴
1乳児脂漏性皮膚炎
| 特徴 | 生後2~3か月頃に多く見られ、頭皮、顔、耳の周り、首などに黄色いかさぶたや脂っぽい湿疹ができます。 |
|---|---|
| 原因 | 母体由来のアンドロゲン(男性ホルモン)の影響で皮脂分泌が過剰になることが主な原因です。 |
| 治療法 |
|
2アトピー性皮膚炎
| 特徴 | 乳児期のアトピー性皮膚炎は顔面周辺に湿疹がでやすいです。乾燥や慢性的な炎症が特徴的で、生後2~3か月以降に発症しやすいです。 |
|---|---|
| 原因 | 遺伝的要因やアレルギー体質に関連し、皮膚バリア機能の低下が原因となります。 |
| 治療法 |
|
3皮脂欠乏性皮膚炎
| 特徴 | 冬季に多く、乾燥した皮膚が白く粉を吹いたようになり、ひび割れやかゆみを伴います。膝下や肘周りに多く見られます。 |
|---|---|
| 皮脂分泌の未成熟 | 乳幼児の皮膚は薄く、バリア機能が未熟。思春期以降に大人と同じ保湿力になります。 |
| 悪化因子 | 冬季、低湿度、過度の入浴や熱いお湯、洗浄力の強い石鹸の使用。 |
| 治療法 |
|
※保湿を1日2回行っても乾燥が続く場合は、湿疹の可能性も高くなります。
特に乳幼児期の湿疹は食物アレルギーのリスクをあげるという研究結果が最近でているので、早めの皮膚科受診をおすすめいたします。
4オムツかぶれ
尿や便が長時間触れたり、湿潤環境が長く続くことにより、オムツが当たる部分に湿疹ができるものです。
| 治療法 | 下痢が続く場合は、当院小児科でフォローいただき、下痢の治療をしながら、皮膚炎に対して、外用薬を処方いたします。 |
|---|
5よだれかぶれ
よだれや食べ物が口回りに付着し、赤みやがさがさが出ている状態です。
| 治療法 | 湿疹の薬で治療し、口回り保護の薬で、口回りを保護します。 |
|---|
虫刺され
蚊やダニ、ノミ、ブヨ、毛虫など、さまざまな虫に刺されることで、赤み・腫れ・かゆみをおきます。
治療
虫刺されの治療は、かゆみを抑えることが最優先です。抗ヒスタミン薬の内服やステロイド外用薬使用します。外遊びの際は、長袖・長ズボンを着られる、市販の虫よけスプレーを活用するなど、予防対策を行いましょう。
伝染性膿痂疹(とびひ)
原因
黄色ブドウ球菌や連鎖球菌が皮膚の小さな傷や湿疹を通じて感染する皮膚病です。
特に子どもに多く、他の部位や他人に広がることがあります。小さな水ぶくれが出るタイプと茶色や黄色のかさぶたが多く出るタイプがあります。
治療
1 抗菌薬
- 抗菌外用薬を塗布。範囲が広い場合や、外用では効果が乏しい場合、内服抗菌薬を使用します。
2 清潔ケア
- 石鹸で洗い、清潔な状態を保ちます。洗った後、薬を塗り、感染拡大防止のためにもガーゼで保護します。
伝染性軟属腫(水いぼ)
伝染性軟属腫ウイルスによる皮膚感染症で、特に子どもに多く見られます。直径1~5mmほどの半透明のいぼで、中央がくぼんでいるのが特徴です。
症状と感染経路
| 症状 | 脇、腕、胴体、太ももなどに数個から数十個のいぼが現れる。かゆみを伴う場合もあります。 |
|---|---|
| 感染経路 | 直接接触やタオル・衣類の共有を通じて感染。プールや運動時に広がりやすい。 |
治療法
1 摘除(ピンセット治療)
- 麻酔テープを使用後、専用ピンセットでいぼを除去します。処置後当日からお風呂やシャワーが可能です。
2 自然治癒
- 1~1.5年で7割の方が自然に治ることが報告されていますが、かゆみや感染拡大を防ぐため早めの治療が推奨されます。
※摘除希望の場合は事前に一度お電話にてお問い合わせください。
尋常性乾癬(イボ)
原因
イボはヒトパピローマウイルス(HPV)が皮膚に感染して発症します。感染経路は、感染者との直接接触やタオル・足ふきマットの共有など。イボが一か所にできると、他の部位にも広がることがあります。
治療法
| 液体窒素凍結療法 (第一選択) |
-196℃の液体窒素をスプレーで患部に噴霧し、ウイルス感染部分を破壊します。治療中に痛みを伴いますが、2週間程度でかさぶたが脱落します。 |
|---|---|
| 内服薬 | ヨクイニン(漢方薬): 免疫力を高め、イボの改善を助けることがあります。 |
| はり薬+外用薬 (保険適応外) |
痛みが苦手なお子さん向けの自費診療(保険適応外)の治療も可能です。 |
汗疹(あせも)
汗疹(あせも)は、汗をかいた後に皮膚の毛穴ができ、赤いブツブツや小さな水ぶくれができる状態です。 赤ちゃんや子どもは体表面積が小さいにも関わらず、大人と汗腺の数が同じなので、あせもを生じやすい状態といえます。特に夏場や湿気の多い時期に発症しやすくなります。
症状
症状は、軽いものでは赤いポツポツした湿疹が現れ、かゆみや痛みを伴います。
治療
治療は、汗をかいたらこまめに拭く、シャワーで洗い流すなど、皮膚を清潔に定めることが基本です。 かゆみが強い場合には、ステロイド外用薬を使用します。
予防としては、通気性の良い服を選び、涼しい環境を整え、汗を吸いやすい素材の肌着を着ることが大切です。
花粉症
症状
花粉症は、スギやヒノキ、ブタクサなどの花粉の原因で、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・かゆみなどの症状がでます。日本人の4~5割の人が花粉症という報告があります。特に子どもの花粉症は、鼻水が長くなってしまって副鼻腔炎を併発したり、目をこすりすぎて結膜炎になったりすることもあります。
治療
治療には、抗アレルギー薬の内服や点鼻薬、点眼薬を使います。花粉シーズン前からの予防が重要で、外出時のマスク着用、帰宅後の洗顔・うがい、室内の換気対策、シーズン前からの抗アレルギー薬の内服開始をするとよいと言われています。
かぶれ(接触皮膚炎)
皮膚が外部の物質(金属、化粧品、植物、ゴム製品など)と接触し、アレルギー反応を起こして、赤み、痒み、腫れなどが起こる疾患です。
診断
| 問診、視診 | 使用した製品や生活習慣を確認し、症状の観察をします。 |
|---|---|
| パッチテスト | 使用している化粧品やシャンプーなどを持参していただき、上腕外側あるいは上背部に貼付して検査を行います。
48時間後再診し、貼付したものを剥がして判定し、72時間後と1週間後にも判定して最終的な結果となります。 金属アレルギー検査もこちらの検査で行います。 |
治療
| 原因物質を避ける | 改善の第一歩です。 |
|---|---|
| 外用薬 | ステロイド外用薬で炎症とかゆみを抑えます。 |
| 内服薬 | かゆみが強い場合に抗ヒスタミン薬を使用します。 |
| 生活指導 | 原因物質の特定と再発防止策をアドバイスします。 |
食物アレルギー
食物アレルギーは、特定の食べ物を食べた後、皮膚・消化器・呼吸器にアレルギー症状が出る病気です。乳児期では卵・牛乳・小麦が原因となることが多く、成長とともに改善するケースもあります。
症状
症状は、じんましん・腹痛・嘔吐・喘息のような呼吸困難などが挙げられます。
検査方法
食物アレルギーの検査には血液検査やプリックテストなどがありますが、検査だけでなく、実際に食べて症状がでるのかという点が診断においてとても重要になります。診断が確定したら、必要最低限の除去により経過を見ていきます。
特徴
乳幼児期の食物アレルギーは、就学前までに9割の方が食べれるようになると言われています。学童期以降にでてくるソバや甲殻類などのアレルギーなどは、治りにくく、原因となる食物を避けるようにして頂きます。
「どこまで除去すればいいの?」「少しずつ食べさせてもいい?」「ナッツアレルギーってナッツ全部食べちゃだめなの?」などのような疑問がある方は、お気軽にご相談ください。
花粉食物アレルギー症候群(PFAS)
花粉食物アレルギー症候群(PFAS)は、花粉症のある人が特定の果物や野菜を食べたときに、口や喉にかゆみや違和感などを感じるアレルギー疾患です。
例えば、
- スギ花粉症の人 → トマト
- シラカバ花粉症の人 → リンゴ・モモ・ナシ
- ブタクサ花粉症の人 → メロン・スイカ
など、花粉と似た成分を持つ食べ物を食べると、アレルギー反応が起こることがあります。
症状
症状は、口の中のかゆみ・イガイガ感・喉の腫れなどが多く、通常は軽いですが、まれにアナフィラキシー(全身の強いアレルギー反応)を起こすこともあります。加熱すると症状が出にくくなることが多いため、「生のリンゴはダメでも、アップルパイなら大丈夫」というケースもあります。
気になる症状がある方は、原因を特定するための検査や、適切な対処法についてご相談ください。
金属アレルギー
ピアスやネックレス、腕時計、ベルトのバックル、歯科治療で使う金属など、肌に触れる金属が原因でかぶれや湿疹が出ることがあります。
原因となる金属
- ニッケル(アクセサリー、腕時計、金属メガネなど)
- コバルト(金属メッキ、塗料など)
- クロム(革製品、金属加工品など)
- 金・銀・パラジウム(歯科用金属、アクセサリー)
診断・治療
- パッチテストで原因金属を特定します。
- かぶれが強い場合は、ステロイド外用薬や抗ヒスタミン薬を使って炎症を抑えます。
- 金属製品を避ける、樹脂製やチタン製のアクセサリーを選ぶことで予防できます。
「アクセサリーをつけると耳がかぶれる」「ベルトの金具部分が赤くなる」などの症状がある方は、一度ご相談ください。
ダニアレルギーに対する舌下免疫療法
ダニアレルギーによるアレルギー性鼻炎の治療法として、舌下免疫療法があります。この療法は、ダニ由来のアレルゲンを少量ずつ舌の下に投与し、体を慣らしていくことで、アレルギー反応を和らげることを目指します。
どんな人におすすめ?
- ずっと鼻水がでているが、秋ごろに特に悪化する方
- ホコリが多いところに行くと、くしゃみや鼻みずが止まらない方
舌下免疫療法のメリット
- 症状の緩和: 鼻症状の改善が期待できます。
- 薬剤使用量の減少: 対症療法薬の使用量を減らせる可能性があります。
- 長期的な効果: 適切に行えば、効果が長期間持続することが報告されています。
治療法
1 診断
症状から疑い、検査などを行い、ダニアレルギーによるアレルギー性鼻炎の診断を受けます。
2 治療開始
少量のアレルゲンを舌下に投与し、徐々に増量していきます。
3 維持療法
適切な維持量を年単位で継続的に投与します。
効果を得るためには、3~5年程度の継続的な治療が推奨されています。
注意点
- 医師の指導のもとで行う: アレルギー領域の専門的知識と経験を持つ医師のもとで施行することが重要です。
- 副作用の可能性: 口腔内のかゆみなどの副作用が生じることがありますが、多くの場合は軽度で一過性です。
舌下免疫療法は、アレルギー疾患の自然経過を修飾し、全身的・包括的な臨床効果が期待できる治療法として位置づけられています。ダニアレルギーによる症状でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
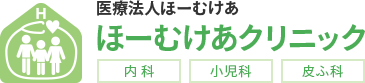


 外来予約
外来予約 Web問診票
Web問診票